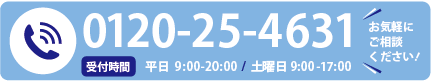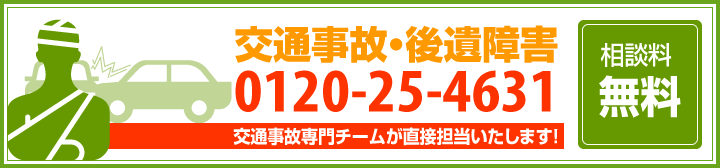突然の交通事故により「腰椎破裂骨折」という大変重いお怪我を負われたご本人様、そして、その方を懸命に支えていらっしゃるご家族の皆様へ。
腰椎破裂骨折は、激しい痛みを伴うだけでなく、その後の生活にも大きな影響を及ぼす可能性のある深刻な傷病です。現在、治療に専念されているあるいは後遺症でお悩みのことと思いますが、同時に、先の見えない不安、治療費や生活費への心配、そして今後の保険会社とのやり取り、今後の補償など、多くのご心労を抱えていらっしゃることと存じます。
「治療はいつまで続くのだろうか…」
「元の身体に戻れるのだろうか…」
「仕事に復帰できるのだろうか…」
「保険会社から提示された金額は妥当なのだろうか…」
本記事では、交通事故案件を専門的に取り扱う弁護士の立場から、腰椎破裂骨折に関する後遺障害等級、慰謝料の目安、そして適正な賠償金を受け取るための重要なポイント等について、できる限り分かりやすく、詳しく解説いたします。
腰椎破裂骨折とは?── 放置できない深刻な骨折、圧迫骨折との違い

まず、腰椎破裂骨折がどのような状態なのか、正しく理解することが重要です。
腰椎破裂骨折とは、交通事故の強い衝撃などによって、腰の背骨である腰椎が、前方・後方・上下方向から激しく押しつぶされ、骨が粉々に砕けてしまうような重度の骨折を指します。
この骨折の深刻な点は、砕けた骨片が、背骨の中を通る非常に重要な神経の通り道である「脊柱管(せきちゅうかん)」に飛び出してしまう可能性があることです。脊柱管内の神経(脊髄や馬尾神経など)が損傷を受けると、下肢の麻痺やしびれ、排泄障害といった、非常に重い後遺症につながる危険性があります。
【圧迫骨折との違い】
よく似た傷病名に「圧迫骨折」がありますが、両者は重症度が大きく異なります。
• 圧迫骨折: 主に上下方向からの力で骨が「潰れる」ように骨折します。比較的軽度で済むケースもありますが、程度によっては変形や痛みが残ることもあります。
• 破裂骨折: 骨が前後左右にも「破裂・粉砕」するように壊れるため、骨片が周囲に飛び散りやすく、神経損傷のリスクが圧迫骨折よりも格段に高くなります。 治療が長期化し、重篤な後遺障害が残りやすい、より深刻な骨折と言えます。
【腰椎破裂骨折が起こりやすい事故の状況】
• 自動車・バイクの衝突事故: 特に、正面衝突や追突事故など、強い衝撃が加わるケース。
• 高速道路での玉突き事故: 衝撃が連鎖し、予期せぬ強い力が腰部に加わることがあります。
• 自転車事故や歩行中の交通事故: 車にはねられたり、転倒したりする際に腰を強打した場合。
• 高所からの転落事故: 工事現場や階段などからの転落も原因となります。
腰椎破裂骨折の治療の流れと長期的な後遺症リスク

腰椎破裂骨折と診断された場合、一般的には以下のような流れで治療が進められます。
① 入院による安静: まずは骨折部位を安定させ、さらなる神経損傷を防ぐため、ベッド上での安静が指示されます。
② 保存療法(コルセット等による固定): 神経損傷がない、あるいは軽微で、骨のずれが少ない場合は、硬質のコルセットや装具を用いて、骨が癒合するまで長期間(数ヶ月単位)固定します。
③ 手術療法
④ リハビリテーション: 状態が安定したら、理学療法士などの専門家の指導のもと、早期からリハビリテーションを開始します。寝たきりによる筋力低下や関節拘縮(固まってしまうこと)を防ぎ、歩行訓練や体幹の筋力回復訓練などを段階的に行い、日常生活や社会復帰を目指します。
腰椎破裂骨折の日常生活への影響について
■ 腰椎破裂骨折とは、絶対安静が必要な重大なけが
交通事故などで腰椎破裂骨折を負った場合、絶対安静が何よりも重要です。これは、骨が粉砕され、わずかな動作でも神経や脊椎へのさらなる損傷につながるリスクがあるためです。
■ 腰椎破裂骨折で「やってはいけない動作」(禁忌)
腰椎破裂骨折を負った場合、腰に負担がかかる動きは厳禁です。以下のような動作は避けましょう。
・腰をひねる
・腰を曲げる
・落とした物を拾う動作
これらはすべて腰椎に強い負荷がかかるため、骨折の悪化や治癒遅延の原因となります。
■ コルセットで腰を固定し、腰への負担を最小限に
日常生活では、コルセットなどの装具を使用し、腰椎をしっかりと固定することが勧められます。体幹の動きを最小限にすることで、骨の癒合を助け、神経損傷のリスクも減らすことができます。
■入院期間の目安と仕事復帰の可能性
腰椎破裂骨折の中でも、椎体の損傷が大きい場合には、椎体間固定術(インストゥルメンテーション)などの手術が必要になります。このような場合、入院期間はおおよそ2か月程度が目安とされています。
■ 仕事復帰は可能なのか?
手術後も安静とリハビリが必要ですが、状態が安定すれば仕事復帰は可能です。ただし、復帰時期は業務内容や個人の体力にもよるため、医師のアドバイスを受けながら判断することが望ましいでしょう。
当事務所の解決事例でも、ご依頼者様は、後遺症が残りつつも仕事に復帰されています。
後遺症として残る可能性のある症状・影響
残念ながら、懸命な治療やリハビリを行っても、以下のような症状や影響が残ってしまうケースは少なくありません。
• 慢性的な腰痛や下肢の痛み・しびれ: 神経の損傷や、背骨の不安定性、変形などが原因で、常に腰や足に痛みやしびれを感じる状態。天候によって悪化することも。
• 体幹の可動域制限: 背骨が固まってしまい、体を反らす、捻るなどの動きが以前のようにできなくなる。日常生活での動作(靴下を履く、物を拾うなど)に支障が出ることも。
• 就労への影響:
・重い物を持つ作業が困難になる
・長時間の立ち仕事や座り仕事が辛くなる
・以前と同じような肉体労働や運転業務などができなくなる
など、仕事の内容によっては、配置転換や転職を余儀なくされるケースもあります。
• 脊柱の変形: 背骨が後ろに曲がってしまう後彎(こうわん)変形や、横に曲がる側彎(そくわん)変形などが残ることがあります。見た目の問題だけでなく、痛みの原因やさらなる機能障害につながることも。
腰椎破裂骨折の後遺障害等級は何級?

十分な治療を継続しても、残念ながら上記のような症状が改善せず、症状が残ってしまった場合、「症状固定」という段階を迎えます。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても、医学的に大幅な改善は見込めない」と医師が判断した状態を指します。決して「治った」という意味ではありません。この症状固定の診断を受けた後、残ってしまった症状について、「後遺障害」(後遺症)として認定を受けるための申請手続きを行います。
後遺障害の等級は、症状の重さに応じて1級から14級(および要介護の別級)まで定められており、腰椎破裂骨折の場合、主に以下のような等級に認定される可能性があります。
【腰椎破裂骨折における後遺障害等級の目安】
| 等級 | 症状 |
|---|---|
| 6級5号 | せき柱に著しい変形を残すもの せき柱に著しい運動障害を残すもの |
| 8級2号 | せき柱に運動障害を残すもの |
| 11級7号 | せき柱に変形を残すもの |
■後遺障害6級5号の条件
以下が、画像所見により確認できること。
① 脊椎圧迫骨折等により、2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が発生していること。
→減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上であるもの。
②せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
→「前方椎体高が減少」したとは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であるもの。
または、腰部が強直(可動域が10度以下)したものをいいます。
■後遺障害8級2号の条件
① 腰椎のにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがX線写真等により確認できる
② 腰椎にせき椎固定術が行われたもの
③ 腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
上記①〜③のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(通常曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。
■後遺障害11級7号の条件
① せき椎圧迫等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる場合
② せき椎固定術が行われた場合
③ 3個以上のせき椎について、椎弓切除等の椎弓形成術を受けたもの

後遺障害等級認定の重要性
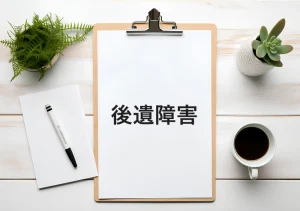
後遺障害の等級認定について
後遺障害は、慰謝料等の保険金に大きな影響を及ぼします。
後遺障害の等級認定は、医師の診断書を元に損害保険料率算出機構が行いますが、被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。
つまり、考えていたよりも低い等級で認定されてしまったり、等級がつかない「非該当」とされることもあります。
適正な後遺障害の認定を受けるためには、適切な治療を受け、適切な検査を受け、適切な行為障害の診断書を作成してもらうことは、重要です。
同じ症状でも、医師がどのような治療を選択するか、検査を選択するかは、全く違います。また、診断書の書き方も全く違います。
従って、適切な後遺障害の認定を受けるためにも、受傷直後、症状固定前から、弁護士に相談されることが重要です。
後遺障害の慰謝料と逸失利益について
適切な後遺障害等級の認定を得ることは、適正な賠償を受ける上で最も重要なステップと言っても過言ではありません。
後遺障害等級が認定されると、主に以下の損害賠償を請求することができます。特に慰謝料と逸失利益は、金額が大きくなる傾向があります。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことによる精神的な苦痛に対する補償です。等級に応じて、おおよその相場(裁判を起こした場合の水準=裁判基準・弁護士基準)が決まっています。
| 後遺障害等級 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 | 100/100 |
| 第2級 | 2,370万円 | 100/100 |
| 第3級 | 1,990万円 | 100/100 |
| 第4級 | 1,670万円 | 92/100 |
| 第5級 | 1,400万円 | 79/100 |
| 第6級 | 1,180万円 | 67/100 |
| 第7級 | 1,000万円 | 56/100 |
| 第8級 | 830万円 | 45/100 |
| 第9級 | 690万円 | 35/100 |
| 第10級 | 550万円 | 27/100 |
| 第11級 | 420万円 | 20/100 |
| 第12級 | 290万円 | 14/100 |
| 第13級 | 180万円 | 9/100 |
| 第14級 | 110万円 | 5/100 |
6級だと1180万円、8級だと830万円等、等級によって違いがあることがおわかりかと思います。
※注意: これはあくまで裁判基準(弁護士基準)の目安です。保険会社が当初提示する金額(自賠責基準や任意保険基準)は、これよりも大幅に低いことが一般的です。
(2)入通院慰謝料
事故による怪我の治療のために、入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への補償です。入通院の期間や日数、怪我の程度によって算定されます。腰椎破裂骨折のような重傷の場合、入院期間も長くなる傾向があるため、100万円〜200万円以上となるケースも少なくありません。これも裁判基準(弁護士基準)で計算すると、保険会社の提示額より高額になることがほとんどです。
慰謝料の計算には、自賠責保険基準、任意保険基準、そして弁護士基準(裁判基準)の3つの基準がありますが、弁護士が介入した場合や裁判になった場合は、最も高額となる傾向にある弁護士基準で計算します。
破裂骨折など、重い怪我の場合は、より高額な慰謝料基準が適用されます。
慰謝料は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)と言われる専門書に記載されている表が、基本的に基準として採用されています。
以下では、裁判基準の表を公開します。

・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
(別表Ⅰの例)
①通院6か月のみ→116万円
②入院3ヶ月のみ→145万円
③通院6か月+入院3ヶ月→211万円
(3)逸失利益
後遺障害によって、事故前のように働くことができなくなり、将来得られるはずだった収入が減少してしまうことに対する補償です。後遺障害による逸失利益」は、事故によって体に痛みが生じたり、関節が動かしにくくなる(可動域制限)などの後遺障害が残ってしまったことで、労働能力が低下し、将来の収入の減少が予想される場合の減収に対する補填をいうのです。
これは、被害者の方の将来の生活設計に直結する、非常に重要な項目です。
【逸失利益の計算式(基本的な考え方)】
基礎収入額(事故前年の年収など) × 労働能力喪失率(等級ごとに定められている) × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(※)
• 労働能力喪失率: 後遺障害によってどの程度働く能力が失われたかを示す割合。等級ごとに目安が定められています(例:8級=45%、10級=27%、12級=14%、14級=5%)。
• ライプニッツ係数: 将来受け取るはずだった収入を前倒しで受け取るため、中間利息(運用益)を差し引くための係数。就労可能年数(原則67歳まで)に応じて決まります。
【具体例】
たとえば、事故前の年収が500万円の40歳の方が、腰椎破裂骨折で後遺障害8級(労働能力喪失率45%)に認定され、67歳まで働くと仮定した場合、
500万円 × 45% × (67歳までの27年間に対応するライプニッツ係数)
となり、ライプニッツ係数にもよりますが、数千万円単位の逸失利益が認められる可能性があります。
このように、後遺障害等級が適切に認定され、裁判基準(弁護士基準)で慰謝料や逸失利益を計算すると、賠償額は非常に高額になります。
だからこそ、保険会社の提示を鵜呑みにせず、専門家によるチェックを受けることが不可欠なのです。
保険会社との示談交渉における落とし穴

治療が終了し、後遺障害等級が認定される(あるいは非該当となる)と、いよいよ加害者側の保険会社との示談交渉が本格化します。しかし、ここに大きな落とし穴が潜んでいます。
保険会社が提示してくる示談金額は、ほとんどの場合、法的に認められるべき正当な金額よりも低いと考えてください。なぜなら、保険会社は営利企業であり、支払う保険金をできるだけ抑えようとするインセンティブが働くためです。彼らが提示する金額の算定基準は、主に以下のいずれかです。
• 自賠責基準: 法律で定められた最低限の補償基準。
• 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している内部基準(非公開)。
これらは、前述した、裁判基準(弁護士基準)と比較すると、特に慰謝料や逸失利益において、数百万円から、重い後遺障害の場合は数千万円単位で差が出ることも珍しくありません。
【示談交渉でよくあるトラブル】
• 提示された慰謝料額が、裁判基準と比べて極端に低い。
• 後遺障害等級が、実態よりも低い等級で認定されたり、「非該当(等級なし)」と判断されたりする(事前認定)。
• 将来の減収(逸失利益)が全く計算されていない、または不当に低く見積もられている。
• 「これが最終提示です」「これ以上は出せません」「早くサインしないと打ち切ります」などと、心理的なプレッシャーをかけ、示談を急かされる。
• 過失割合について、被害者側に不利な主張をされる。
交通事故の被害者の方は、身体的な苦痛に加え、こうした保険会社との専門的で煩雑な交渉に、精神的にも疲弊してしまうことが少なくありません。知識や経験が不足していると、知らず知らずのうちに不利な条件で示談に応じてしまうリスクがあります。
このような状況を打開し、適正な賠償額を獲得するためには、交通事故問題に精通した弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士が介入することで、保険会社は裁判基準(弁護士基準)を検討することになります。
なぜ弁護士? 依頼するメリットと相談のベストタイミング

「弁護士に頼むと費用がかかるのでは?」「大げさにしたくない」と思われるかもしれません。しかし、特に腰椎破裂骨折のような重傷事案においては、弁護士に依頼することで得られるメリットは非常に大きい場合があります。
【弁護士に依頼する主なメリット】
• 適正な後遺障害等級の獲得に向けたサポート:
・ 後遺障害診断書の記載内容について、医学的知見に基づきチェックし、医師に対して適切な記載を依頼・アドバイスします。
・ 等級認定に有利となる画像所見や検査結果の収集をサポートします。
・ 複雑な申請書類の作成・提出を代行します。
・ もし、納得のいかない等級認定結果が出た場合でも、異議申立ての手続きを適切に行います。
• 賠償金の増額交渉:
・ 慰謝料、逸失利益などを漏れなく、最大限請求します。
• 保険会社との交渉窓口の一本化:
・ 被害者の方に代わって、保険会社との全ての連絡・交渉を行います。これにより、煩わしいやり取りから解放され、治療やリハビリ、生活の再建に専念できます。
• 訴訟への対応:
・ 万が一、交渉で合意に至らない場合でも、訴訟(裁判)手続きに移行し、裁判所を通じて適正な賠償の実現を目指します。
【相談のベストタイミングは?】
なぜなら、
• 適切な後遺障害等級認定を得るためには、症状固定前から計画的に検査を受けたり、医師との連携を図ったりする必要があるからです。
• 早期にご相談いただくことで、今後の見通しや取るべき対応について、弁護士が戦略を練るための十分な時間を確保できます。
• 治療中の段階から保険会社との対応についてアドバイスを受けることで、不利な状況に陥るのを防ぐことができます。
もちろん、既に症状固定の診断を受けた後や、保険会社から示談案の提示を受けた後でも、決して遅すぎることはありません。少しでも疑問や不安を感じたら、まずは一度ご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所の交通事故解決実績

私たちグリーンリーフ法律事務所は、交通事故案件を重点的に取り扱う法律事務所として、これまで数多くの交通事故被害者の方々をサポートしてまいりました。
特に、腰椎破裂骨折をはじめとする脊柱骨折などの重傷事案においては、豊富な経験と実績を有しております。後遺障害等級の認定サポートから、保険会社との粘り強い交渉、必要に応じた訴訟対応まで、専門知識を駆使し、依頼者の方にとって最善の結果を追求いたします。
【当事務所での解決事例(一例)】
・腰椎圧迫骨折で後遺症11級7号、賠償額670万円(治療費除く)を交渉で獲得したケース
https://www.g-koutujiko.jp/jirei/20231113-1/
・頚椎骨折等により併合7級の認定を取得し、合計2700万円の保険金を取得した事例
https://www.g-koutujiko.jp/jirei/102/
交通事故による大腿骨骨折について弁護士に依頼するメリットまとめ

後遺障害が残ると保険金額が大きくなるので保険会社と争いになることがほとんどです。
特に、慰謝料や逸失利益は金額が大きくなります。
弁護士に依頼するのとしないのでは、数十万~事案によって数千万円の違いがでる可能性もあります(実際に当事務所でありました)。
弁護士に依頼をすることによって、保険会社との交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。
こうした事がメリットになります。
ラインでの相談も行っています。友達登録して、お気軽にお問い合わせください。
弁護士特約については、こちらをご覧ください。
【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。
弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。弁護士費用特約で、自己負担一切なしのケースもあります。
弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内でおさまります。
ご相談 ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
入院中でお悩みの方や、被害者のご家族の方に適切なアドバイスもできるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。